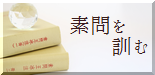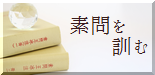【論旨】
《 Ⅰ 》
瘧を足の太陽、少陽、陽明、太陰、少陰、厥陰の六類に分類して、各々の症状、刺法を論ずる。症状が現れる場所によって太陽や少陽などの分類をしているのであり、傷寒論のような熱の深浅や、病の進行度合いを表しているのではない。
【 考 察 】
解㑊カイエキ・・・素問攷注でも18行を費やして長々と説いているが、「而れども、いまだ明説有らず」なのである。問題は「㑊」の字義で、どう解釈すべきか。手元の小版の辞書には「㑊」は採られていない。大漢和辞典(大修館)では採取されてあるが、素問・通評虚実論の例を引くだけで余計な解説はない。用例を載せるのが辞書の本義であるとする本道に基づくなら、まことに潔い。
字統(白川静)には「亦」について、人を正面から見た象形である、にはじまる説明がある。解決につながる記述は、声義として通用する字に「又(ユウ)」「有(ユウ)」「或(ワク)」があるという箇所である。「或」には「まよう」「あやしむ」の義がある。とするなら「人の身體をして解㑊せ令む」は体に力が入らなくなって、グダグタになってしまうことである。意は通ずる。
ポイントは、音(声)が近いものは義(意味)も近いことがあるということで、こういう事情にピンと来る感覚が、漢語文を理解するうえで大切である。「エキ」と「ワク」は全く音が違うではないかと言いたくなるが、古代漢語のことゆえ、音はやや異なるだろう。「エキ」が「ヱク」、「アク」に転ずることを考えれば「ワク」にはすでに近い。
《 Ⅱ 》
瘧を、症状、顔色などによって、どの藏に関する瘧であるかを論ずる。五藏に加えて、胃瘧の分類を設けて六つに分類している。治療も、肺瘧ならば手の太陰と陽明、心瘧ならば手の少陰と、藏に対応する経を取る。
【 考 察 】
「胃瘧は、且(も)し人をして病ましむるや」と私は無理をして訓じたが、やはり、すなおに「且(まさ)に人をして病ましめんとするや」と訓むべきだろう。
《 Ⅲ 》
発作が起って発熱しようとするときは、「跗上の動脈」(足背動脈)を瀉血し、凍えの発作が出はじめたときには、手足の陽明、太陰を刺せと論ずる。
続けて、瘧の脈が①満、大、急 ②小、実、急 ③満、大、急 ④緩、大、虚 以上四種類の時の治療法を論ずる。
【 考 察 】
①と③は脈が「満、大、急」で同じであり、刺法も①「刺背兪。用中鍼、傍伍胠兪、各一。適肥痩、出其血也」、③「刺背兪。用伍胠兪、背兪、各一。適行、至於血也」と、ほぼ同一である。じつは、この③の刺法についていえば、王冰が通評虚実論より移続したものであると新校正が注している。よって新校正は、これを刪去すべしと論じている。
これに対して森立之は「素問攷注」において「この一條、太素にこれ有り。新校正、後文に、『詳しくは前の瘧脈、滿、大より此れに至るは、全元起本第四巻中に在り。王氏、ここに移續したる也』という。これに據れば全(元起)本もまた載すると知るべき也。然らば古来より此の條、重複してここに在り。但し其の文、小さく異なれり。前にいう中鍼はここに第五鍼と云う。前にいう傍伍胠兪は、ここに胠兪と云う。前にいう適肥痩出其血は、ここに適行至於血と云う也。其の文義、互いに相發すれば、輒刪すべからざる也。此の如き文例、甚だ多く、文中に自ずから經傳を相い爲すなり」と論じている。立之の面目躍如といったところである。
《 Ⅳ 》
瘧の発作が起ったときは、間髪を入れず、ただちに治療せよと論ずる。
指間穴を瀉血すれば必ず発作はおさまる、体の細絡はことごとく瀉血せよと言い、十二經脈の瘧はそれぞれ現れ方が違うから、その違いを見きわめて、どの脈の瘧かを見定めよと論ずる。
《 Ⅴ 》
発作時に頭の痛むものは頭を刺し、項背の痛むものは、まず項背を刺して瀉血せよと、症状の最初に現れる場所を刺絡することを論ずる。
《 Ⅵ 》
風瘧、身体小痛する場合、一日おきに発作の起こるもの、温瘧の場合などを、個々に論ずる。
【 考 察 】
瘧論、刺瘧篇を通じて、楊上善の注釈が虹彩を放っている。楊上善は太素のなかに「十二瘧」を設けて瘧の治療を包括的に論じているが、心瘧には少海、脾瘧には大都、公孫、商丘、凍えの発作のときには商陽、三間、合谷ほか、というふうに、逐一、治療穴を詳細にあげている。7世紀に、このような治療法を完成させていたということは、驚くべきことではないだろうか。
また、Ⅲ部の「中鍼」とは、中程度の鍼ではなく、九鍼の真ん中の鍼=鈹鍼(䤵鍼)を指すと論じている。同じくⅢ部の「用伍胠兪。背兪、各一」は、正しくは「用五。背兪、伍胠各一」であると素問の条文の不正確を看破して、見事である。「用五」とは「中鍼」と同じであり、「九鍼中の第五鍼を用いよ」ということに他ならない。
|