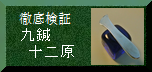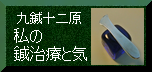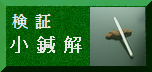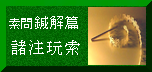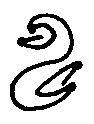多紀桂山「本經は多(おほ)く篇字、論字を下さず。乃ち古書たる所以なり」 |
【第一部】 |
【第一部】<一> 黄帝が歧伯に微鍼による萬民の治療を求める |
1 黄帝問於歧伯曰、余子萬民、養百姓而収租税。
2 余哀其不給(終_太素)而屬有疾病。
3 余欲勿使被毒薬、無用砭石。
4〈欲以_酌原堂明刊本〉微鍼、通其經脈、調其血氣、營其逆順出入之會。
5 令可傳於後世、必明爲之法。
6 令終而不滅、久而不絶、易用難忘、爲之經紀、異其(篇_太素)章、別其表裏、爲之終始、令各有形、先立鍼經、願聞其情。
|
《読み下し文》
黄帝、歧伯に問ふて曰く、余、萬民を子とし、百姓を養ひて租税を収めしむ。余、其の終らざるを哀れみ、疾病有るを屬(恤-あはれ)む。余、毒薬を被らざらしめ、砭石を用いざることを欲す。微鍼を以て、其の經脈を通じ、其の血氣を調へ、其の逆順、出入りの會を營(めぐ)らさむことを欲す。後世に傳へしめ、必ず明に之を法と爲さむ。終(永遠)にして滅びず、久しくして絶へず、用ゐるに易く忘るるに難からしめ、之を經紀と爲し、篇章を異とし、其の表裏を別け爲めむ。之に終始を爲り、各々形有ら令めむ。先ずは鍼經を立てよ。願はくは其の情を聞かむ。
|
《現代日本語訳》
黄帝が歧伯に問うて言うには、私は万民を自分の子のように思い、百姓を養って租税を収めさせている。しかし民が寿命を迎える前に死ぬ(終)のを哀れみ、また病を得るのを恤(あわれ、=屬)んでいる。私は民が強い薬を飲ませたくないし、砭石で我が身を傷つけたりさせたくない。微鍼をもって経脈を通じ、血気を調え、経脈の流れの逆順・血気の出入りの会(つぼ、経穴)を営(めぐ)らせたいのだ。それを後世に伝えられるよう、誰にでも分るような(明)法とさせたいと思っている。それは永遠であって滅びることなく、ながく続いて絶えず、用いるに易く忘れ難いものとしたい。それを經紀としてつくり、篇章を分け、表裏も別けて、終りと始めをつくって、各々形あるものとしたいのだが、まずは鍼経をつくりたい。どうすればよいか、聞かせてもらいたい。
|
《記》 まず黄帝が求めているのは、「微鍼」を以てする治療である。その治療とは、微鍼を
もって経脈を通じ、血気を調え、経脈の逆順や血気の出入りの会を調える治療で、患部にしろ全身にしろ、強い刺激や薬物で傷めるような治療を求めいないことが、まず述べられる。 |
「余哀其不給而屬有疾病」 給は太素では終、終は寿命を全うするの意。屬は康煕字典では恤に通じ、あわれむの意となると、佐合昌美先生が説いている。
「(欲以)微鍼、通其經脈」 抽齋は酌原堂所蔵の明刊本を原本としていると書いているが、欲以の右肩に小さく善按と書いて、二字を自分で補ったように記している。
「必明爲之法令」 ここは「法令」と熟語にして読みたくはない。しかし、この後の第二 節は四字句としてまとめられているから、令は第一節に入れてしまわなければならない字だという(宮川先生)が、それほど四字句にこだわらなければならないのだろうか。また、「明」は「明らかに」と読んでは、何も表していないことになる。「メイに」と読むほかはなく、顕教・密教の顕、経典・緯典の経を指しているものと考えなくてはならない。
「終而不滅」 終はひさしい。滅はたえる、ほろびる。だから次の「久而不絶」と同じ読みになる。
「異其章」 太素では異其篇章。
|
【第二部】
|
【第二部】<一> 歧伯が微鍼治療のための經の編纂を開始する
|
7 歧伯答曰、臣請推而次之、令有綱紀、始於一、終於九焉。請言其道。
|
《読み下し》 歧伯答へて曰く、臣、請ふ、推して之に次で、綱紀有ら令しめむ。一に始り、九に終ら令めむ。其の道を言はむことを請ふ。
|
《現代日本語》 歧伯が答えて言うには、まずは熟慮(推)させていただき、その後綱紀をつくりたいと思います。第一篇に始まり、第九篇で終るものとなります。どのようなものか申し上げます。 |
【第二部】<二> 微鍼による治療での神(精神集中と、その集中下で行なわれる得気術)の重要性
|
8 小鍼之要易陳而難入。
9 麤守形、上守神、神乎神。
10 客在門、未覩其疾、惡知其原。
|
《読み下し》 小鍼の要は陳ぶるに易く、入るに難し。麤は形を守り、上は神を守る、神なるかな神。客、門に在り、いまだ其の疾を覩ざるに、惡んぞ其の原を知らむ。
|
《現代日本語》 小鍼を用いた治療の要は、言うのは簡単だが、身につけるのが難しいのです。粗工は刺す形を守っているだけだが、上工は鍼治に付随する優れた精神を守って刺します。上工の神技こそ、まさに神威の現れであります。また、邪が体に取り付いたばかりで、まだ病に罹ったといえる状態でもないのに、どのようにしてその原因を見極めるのでしょうか。
|
《記》 ここで歧伯は「小鍼」を用いることについて述べており、小さな鍼を用いれば、黄帝が求めるような経脈を通じ、血気を調えるような治療ができると説いている。黄帝は微鍼といい、歧伯は小鍼と言う、この差をどう理解すべきか。恐らく「小鍼」とは、九鍼の中でも毫鍼などの細く短い鍼のことを指しているのではないか。九鍼十二原の解説である第三篇に「小鍼解」と名づけてあるのも、九鍼十二原の本分が小鍼によって気を集めたり、得気したりすることだからではないか。
|
「小鍼之要易陳而難入」 小鍼とは、この篇で説く九鍼の中でも細く短い鍼のことで、
前に黄帝が述べている「微鍼」のことである。
小鍼解では、「入」を身に着けることと解しているが、九鍼十二原篇では「入」は総じて鍼を刺すことをいっている。しかしながら、ここでは主語は「小鍼之要(小鍼をあつかう要点)」であるから、小鍼解で言うように「身に着ける・会得する」が正しい。
「麤守形、上守神」 粗工は刺す形を守っているだけだが、上工は鍼治に付随
する優れた精神を守って刺す。
「神乎神」 上の神は、すぐれた精神の働き。下の神は、上工の神技をいう。九鍼十二
原篇全体を通じて、鍼を以て気を至らしめる・散ずる技法が必要であることが説か
れ、それに付随して、患部に気が至っているか否かが分る感覚の必要性も説かれる。そうした技術と感覚を神といい、その技術をもった技術者を上工と言っている。
|
神字解 ・・・天の神、精神のすぐれた働き
神-1・金文
|
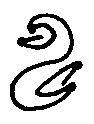 |
|
神-2・金文 |
 |
申は電光が斜めに屈折して走る形で、神威の現れるところ。説文に「天神なり」とし、「萬物を引き出すものなり」と、神・引の畳韻をもって訓ずるが、このような音義的解釈は漢代の語源学に共通のものである。
神は天神で祖霊を含むことはなく、人の霊には鬼という。
神事のみでなく精神のはたらきや、そのすぐれたものを神爽(しんそう)・神悟のように言い、人智を越えるものを神秘という。<白川静『字統』>
|
【第二部】<三> 上工はタイミングを重視していることと、鍼による迎随(逢追・逆順) |
11 刺之微在速遲、麤守關、上守機。
12 機之動、不離其空、
13 空中之機、清静而微。
14 其來不可逢、其往不可追。
15 知機之道者不可掛以髪、不知機道、叩之不發。
16 知其往來、要與之期。
17 麤之闇乎。妙哉工、獨有之。往者爲逆、來者爲順。明知逆順、正行無問。
18 逆(迎_抽齋・明刊本)而奪之、惡得無虚、追而濟之、惡得無實。
19 迎之隨之。以意和之、鍼道畢矣。
|
《読み下し文》
刺の微は速遲に在り。麤(ろ)は關※1を守り、上は機※2を守る。
機の動くや、其の空を離れず。
空中の機は、清静にして微なり。
其の來たるや逢ふ可からず、其の往くや追ふ可からず。
機の道を知れば、髪を以て掛くる可からず、機の道を知らざれば、叩(たた)くも發さず。
〔叩(ひか)へて發さず〕
其の往來を知り、要(かなら)ず之が期※に與(あづか)れ。
(要(かなら)ず之が期を與(な)せ)
麤(ろ)の闇(くら)きかな。妙なるかな工、獨り之れ有り。往く者には逆を爲し、來たる者には順を爲す。逆順を明知し、正行して問ふところ無し。
迎へて奪へば、惡(いづく)んぞ虚無きを得む、追ひて濟(たす)くれば、惡(いづく)んぞ實無きを得む。
迎へよ隨へよ、以て意(おも)ふに、和さむと。鍼道、畢(をは)んぬ。
※1關 88 五藏有六府、(五藏)六府有十二原。
89 十二原出於四關。四關主治五藏、五藏有疾、當取之十二原。
※2機 キ 弩(はじき弓)の弦を引っ掛ける爪と、引き金とからなる発射装置。
きっかけ、きざし、ころあい
※3期 キ (名)一定の時間、(動)望む、待つ
「要與之期」は「期」の意味をどう考えるかによって、三通りの解釈ができる。
1. 気の廻ってくる時間と捉えるなら、「要ず之が期に與れ」と訓じて「必ず気の廻ってくるタイミングに合わせよ」の意になる。
2.治療の期間と捉えるなら、「要ず之の期と與(な)せ」と訓じて、「必ずそこで治療を終りにしろ」の意になる。
3.期待するの意と捉えるなら、「要ず之に期を與(な)せ」と訓じて「それにかけて治療せよ」という意となる。
この場合は、1.の「必ず気の廻ってくるタイミングに合わせよ」と捉えるのが、最も適切と思われる。
|
《現代日本語訳》
粗工は関節にある原穴の位置にだけこだわるものだが、上工は鍼の刺抜や運鍼のタイミングや、気の往来する気配を大事にしている。
発射装置が動いて矢が発射される時には、無心を心がけねばならない。
〔気が廻ってくる気配が感じられた時には、無心を心がけねばならない〕
〔刺抜や運鍼のタイミングが至るに際しては、無心を心がけねばならない〕
無心の心で知ることのできる気の兆しや、鍼のタイミングとは、清静にして微(かす)かなものだ。
気が廻り来る時には、迎え撃ってはならない。また気が去って行く時には、追って留めるように鍼をしてはならない。
気が廻ってくる気配や、鍼のタイミングを知れば、間髪を入れる隙もないことが分るが、分らない工は、叩いても音の鳴らない鼓のようなものだ。
〔手控えてしまうので、鍼を効かせられない〕
気が廻ってきているのか、去ってゆくのかを知り、必ずそのタイミングに合せよ。
〔必ず集中して治療せよ〕
粗工というものは理解がない。それに比べて上工の妙であること、上工だけがそれを会得している。粗工は廻り去る気(正気)を迎え撃とうとし〔寫〕、廻り来る気(邪気)には随おうとしてしまう〔補〕。(上工は)気と鍼技の逆順を正しくはっきりと知っているので、問題となる所がない。
正気が廻ってきている時に、迎えてその正気を寫してしまえば、どうして虚を無くす(=実せしめる)ことができよう。邪気が去って行こうとしている時に、それを追って濟(たす)ければ〔補〕、どうして実を無くす(=虚せしめる)ことができよう。
正しく迎え撃ち、あるいは随うことである。それで病人も治まって行くであろう。〔私の考えもこのような形にまとまった。〕鍼道についてを畢る。
|
「刺之微在速遲」 微は功妙さ。
「不離其空」「空中之機」 ここでいう空とは、鍼を持つときの無心の境地を言うものと思われる。無心であるとき、患者の気の動静が分る。
「其來不可逢、其往不可追」 ここは小鍼解の説くように気がやって来るとき、去ってゆくとき、と解すべきであろう。
「叩之不發」 術者の手際について述べており、粗工の技術は叩いても音の出ない鼓のようなものだと述べている。同時に、「手控えてしまうので鍼を効かせられない」の意も持たせている。
「獨有之」 甲乙經では、「上獨有之」
「麤之闇乎、妙哉工、上(甲乙)獨有之。往者爲逆、來者爲順。明知逆順、正行無問」 ここは粗工と上工の治療について、交互に書かれている条で、いくつかの語を補ってみると分る。このような例は素問などにもあるので、例として次に掲げる。
素問・挙痛論39「所謂、言ふを知ること可なるや、視て見はすこと可なるは奈何」いわゆる、(患者が)訴えて(治療者が)分ることを、(治療者が)視ただけで明からにできるようになるには、どうすればよいか。
素問・八正神明論26「俱に視るに、獨り見る」(皆が)ともに視ているのに、(その人に)独りだけ現れて見える。
論語・学而「人知らずして慍みず」人が分ってくれなくとも、(私は)気にかけない。
《記》この章は「機(弩弓の発射装置)」「(戦闘の鼓を)叩く」など、治療・鍼の技術を戦闘の術に掛けて説く部分がある。
後に出てくる「31 神在秋毫」もそうだが、当時の慣用的な言い回しなのであろう。 |
【第三部】 |
【第三部】<一> 虚法と実法
|
20 凡用鍼者虚則實之、満則泄之、宛陳則除之、邪勝則虚之。
21 大要曰、徐而疾則實、疾而徐則虚。言實與虚、若有若無。
22 察後與先、若存若亡。爲虚與實、若得若失。
23 虚實之要、九鍼最妙。
|
《読み下し文》
凡そ鍼を用るは、虚すれば之を實し、満つれば之を泄らし、宛陳すれば之を除き、邪勝れば之を虚す。
大要に曰く、徐にして疾なれば實し、疾にして徐なれば虚す。實と虚とを言へば、有るが若く無きが若し。後と先とを察すれば、存るが若く亡きが若し。虚と實とを爲せば、得るが若く失ふが若し。虚實の要は、九鍼最も妙なり。
|
《現代日本語訳》
およそ鍼をもって治療する時には、虚している場合には実せしめ(実法)、満ちている場合は泄らし(泄法)、鬱滞しているものは取り除き(除法)、邪が勝っている場合には虚せしめる(虚法)のである。
『大要』には実法と虚法について、鍼をゆっくり刺し、すばやく抜けば、実せしめることができる(実法)。また、刺鍼を早くし、抜鍼をゆっくり行なえば、虚せしめることができる(虚法)、と書いてある。
実と虚がどのような状態かといえば、実とは気が有るがごとき状態で、虚とは気が無きがごとき状態だと書いてある。
治療後とその前を考えれば、(実法の場合は)気が存るがごとくになり、(虚法の場合は)気は亡きが若くになる。虚法と実法を行なえば、気を得ることも失くすことも自在である。
虚法と実法の要については、われわれの称揚している九鍼が最もすぐれている。
|
「宛陳則除之」表立っては「宛」にウツの音はない。しかしながら、史崧(十二世紀、南宋で針経を霊枢として刊行した)が、「宛、音鬱、又音蘊、又於阮切」として「ウツ」音を挙げている。
「大要曰」 当時、『大要』という名の書物があったのであろう。この後の論を読むと、九鍼十二原がまとめられる以前の鍼治療の技術の概要が書かれていた書物だと考えられる。九鍼十二原はこの『大要』よりも新しい内容であることを印象付ける狙いをもって書かれていると考えられる。
抽齋は、大要については、霊枢・衛気行第七十六でも触れられていると紹介している。「大要曰常以日之如(ゆく)於宿上也」
また、この『大要』から引かれた文を理解するうえでも、いくつか語を補わなければ、文の正確な意図が理解できないと思われる。【第二部】<三>(11~18)と同様である。
|
【第三部】<二> 補寫の運鍼法
|
24 補寫之時、以鍼爲之。
25 寫曰(迎之_甲乙)。(迎之_意甲乙)、必持内之、放而出之。
26 排陽、得(出_甲乙)鍼、邪氣得泄。
27 按而引鍼、是謂内温、血不得散、氣不得出也。
28 補曰隨之。隨之意、若妄(忘_甲乙)之、若行、若按、如蟁蝱止、如留、如還。
29 去如絃絶、令左屬右、其氣故止。
外門以閉、中氣乃實。
30 必無留血、急取誅之。
|
《読み下し文》
補寫の時は、鍼を以て之を爲す。寫とは迎へるを曰ふ。迎へるの意は、必ず持ちて之を内(い)れ、放ちて之を出だす。陽を排して、得て鍼を出だせば、邪氣、泄るるを得、按じて鍼を引く。是を内温と謂ひ、血、散るを得ず、氣も出づるを得ざるなり。
補とは隨ふを曰ふ。隨ふの意は、忘るるが若く、行(すす)むが若く、按(おさ)ふるが若く、蟁蝱の止るが如く、留るが如く、還(かへ)す(後をふり返る)が如くす。去るときは絃の絶ゆるが如くす。左をして右に屬(つづ)か令め、其の氣、故に止まる。外門、以て閉じ、中氣、乃ち實するなり。必ず留血を無からしめ、急ぎ取りて之を誅(う)つ。
|
《現代日本語訳》
補法と寫法を行なうには(『大要』には実=実法と虚=虚法という名で 表されていた)、鍼を以て行なう。
寫とは迎えるということである。気を迎えるにはどうすればよいかと言えば、鍼を制 御しつつ内に入れ、抜く時には放つようにして出す。陽気を排するように鍼を抜き出せば、邪気は体外に泄れるのである。この時、鍼孔を按(おさ)えて鍼を引き出すと、内温ということになり、血はそれ以上分散することがなく、正気もそれ以上に体外に出ることがない。
補とは、随うということである。気に随うにはどうすれば良いかと言えば、忘れてしまうほどの時間をかけて、鍼を行(すす)めたり按(と)めたりする。あたかも蟁(カ)や蝱 (アブ)が動物にとまり、あたりを留(うかが)い、後をふり返るごとくに時間をかける。そして、手を放すときは絃が切れるごとくに、左の押し手(鍼を押さえる手)を右の刺し手(鍼を持っている手)に属(つづ)けて、鍼を抜いた時に鍼孔をサッと閉じる。それで、集められた気は体内に留まることになる。外門が閉じるので、中の気は実するのである。出血した場合は、かならず留まらないように、搾り出して取り除いておか なければならない。
|
《記》 この前の【第三部】<一>で九鍼を用いて行なう虚、実、泄、除の四法から、『大要』にしたがって実法と虚法に焦点をあてて論を進めることになったが(19~20)、この<二>では、さらに詳しく補法(実法)、瀉法(虚法)についての手順が説かれている。
|
【第三部】<三> 持鍼の心構え(○)と瀉血法(●)
|
31 ○持鍼之道、堅者爲寶。正指、直刺、無鍼左右。神在秋毫、屬意病者。
32 ●審視血脈者剌之無殆。
33 〇方刺之時、必在懸、陽、及與兩衛。神屬勿去、知病存亡。
34 ●血脈者在腧、横居、視之獨滿、切之獨堅。
|
《読み下し文》
○ 鍼を持する道は、堅きを寶と爲す。指を正し、直く刺せ、鍼を左右すること無かれ。神は秋毫に在れ、意を病者に屬(あつ)めよ。
●審かに血脈を視れば、之を剌すに殆(あやふ)きこと無し。
○方(まさ)に刺さむとする時、心は懸、陽、及び兩衛とに在れ。神を屬(あつ)め、去ること勿らしめば、病の存亡を知る。
● 血脈を取るは腧に在りて横居す。之を視れば獨り滿ち、之を切すれば獨り堅し。
|
《現代日本語訳》
〔○では精神集注について論ずる〕 鍼を持つ要諦は、堅きを宝とする。指を正し、まっ直ぐに刺し、鍼を左右に動かしてはならない。神経を微妙なものに感ぜしめ、気持ちを病人に属(あつ)めよ。
〔●では血絡の治療法を論ずる〕 くわしく血絡を視たら、躊躇なく刺絡せよ。
○ まさに刺そうとする時、意識はかならず懸(鼻筋)、陽(眉の上下)、衛(額)に集めておかねばならない。集中を持続して切れさせなければ、病の行く末も自分の手の内にある。
●血絡は患部のすぐ近くにあるものである。視れば膨れ上がり、触れてみるとそこだけが堅くなっている。
|
「必(心_甲乙)在懸、陽、及與兩衛」 必は甲乙經では心。懸は縣に通じ、はなすじのこと。陽は揚に通じ、眉の上下。衛は太素では衡に作り、眉上。霊枢・論勇に「勇士者、目深以固、長衡直揚」(勇敢な者は、目は静かで動かない、長い額、まっすぐな眉)とある。太素・楊上善注には「先観気色者也、縣陽、鼻也、懸於衡下也、鼻爲明堂、五藏六府気色、皆見明堂及與眉上兩衡之中」とある。(以上、宮川)
|
《記》 ここでは鍼を刺すときの心構えと、瀉血法とが交互に書かれている。この指摘をされたのは、宮川浩也先生である(『季刊内經』No.223)。この心構えが、寫血時の心構えだと読めないこともないが、「神在秋毫、屬意病者」と書かれているのを読むと、瀉血に関する限定的な心構えだけを説いている訳ではないように考えられるのである。
ここまでの論の進め方をみると、【第三部】では初めに、鍼治療には実法、泄法、除法、虚法の四法があると説きながら(19)、『大要』を引いて、実法(補法)と虚法(寫法)の二法だけに限定して論を進めている(20)。泄法や除法を説くならば、九鍼のすべてを用いて行なう治療が説かれることになるだろうが、実際は補法と寫法に論が収斂して、「小鍼」を用いて、集中した精神(神)のもとに無我の境地(空)でタイミング(機)をつかむ、上工の補法・寫法の論に話は進んで行くのである。
もっとも、当初黄帝は、岐伯に「微鍼」を用いた治療の経を立てることを願った(4)のだから、それで良いことになる。その治療とは、毒薬や砭石を用いることなく、微鍼をもって経脈を通じ、血気を調え、経脈の逆順や血気の出入りの会を調える治療なのだから(3~4)、ここまでに論じられてきたことは、黄帝の意を得ているのである。
|